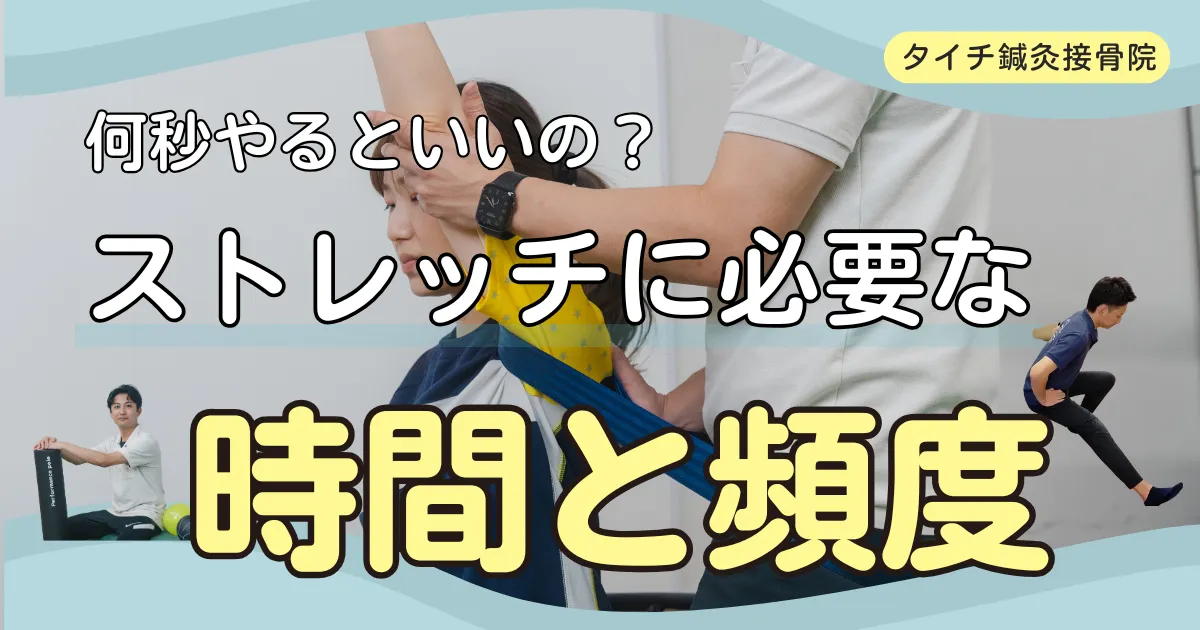あなたの「むくみ」の原因は?原因と対策法について、エビデンスと併せて伝授!
2025/01/17
足の「むくみ」で悩んでいるあなたへ。
むくみ(浮腫)は様々な原因で起こります。そのため、一概に水分の摂りすぎや運動不足が原因とは限りません。
例えば、「足がむくんでいる」と感じていても、むくみと腫れ(腫脹)は異なる症状です。むくみは皮膚の下に水分が溜まり、指で押すと跡が残るのが特徴です。
靴下を履いた後につく痕も特徴的ですね!
本記事では、むくみの原因と対策について詳しく解説します。当てはまる箇所があれば、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 静脈還流の低下(静脈うっ滞)によるむくみ
2. リンパ性によるむくみ(リンパ液の障害)
3. 食事・栄養の影響によるむくみ
4. ホルモン変動によるむくみ
5. 心臓や腎臓の機能低下によるむくみ
6. 肥満によるむくみ
7. 熱中症や高温環境によるむくみ
8. アルコール摂取過多によるむくみ
9. 薬剤性のむくみ
10. 座りすぎや立ちすぎによるむくみ
11. 妊娠によるむくみ
12. 内臓疾患(肝臓・甲状腺など)によるむくみ
13. 筋骨格系によるむくみ(筋肉の影響)
14. ストレスや生活習慣の乱れによるむくみ
1. 静脈還流の低下(静脈うっ滞)によるむくみ
原因
- 長時間の座位や立位による血液循環の停滞:基本的にヒトは重力に逆らいながら生活しますので、長時間動かないでいると血液が末端に滞りむくみとなります。
- 加齢による静脈弾性の低下:加齢により血管の弾力性が低下していきますので、心臓に戻る血管圧が弱まり停滞しやすくなります。
- 静脈弁機能不全(下肢静脈瘤など):特に女性に多く、ふくらはぎの静脈血管が常に浮き出ている状態です。心臓に戻すための弁の機能が低下し、末端に血液が滞る状態です。この場合、一度医師の診断を受けることをお勧めします。
対策
- 運動療法:ふくらはぎの筋ポンプ作用を活性化する軽い運動(つま先立ちや足首回し)が有効です。
- エビデンス: 有酸素運動や軽いレジスタンストレーニングは、静脈還流を改善し、むくみの軽減に寄与することが報告されています(Hirai et al., 2010)。やはり、重力によって血液は足の末端に停滞しますので、足回りの運動は血液を上に戻すのに有効ではありますがその他の関節もしっかり動かすことが重要です。
- 弾性ストッキング:圧迫療法により静脈血の逆流を防ぎ、血流を促進する。
- エビデンス: 圧迫療法が下肢浮腫に効果的であることは多くの研究で支持されています(Partsch et al., 2016)。しかし、ずっと着圧するのではなく、寝る時だけ、仕事の時だけ。などにしましょう。長時間は逆に血流を阻害することがあります。
- 定期的な休憩:座り仕事や長時間立ち仕事の場合、1~2時間ごとに足を動かす。一定時間で一度立ち上がるだけでも有効ですよ!
↓↓↓↓↓↓
タイチ院での対応:
足首の一つだけを動かすのではなく、全身を通して足首の動きを出していきます。
手足のツボに鍼(ハリ)を施術し、そのまま体幹・股関節・足関節を動かし全身的に動かしていきます。
体の歪みも調整した後、個別性のある使われていない筋肉や関節を入念に動かしご自身でもしっかり使う練習を行います。
そうすることで、「自分の体はここまで動かすことができる」という認識に脳に認知させることで日常的に適切な筋肉・関節を使うことができ、全身の血流量UPに貢献しむくみを改善していきます。
そして、日常生活の中でできるセルフトレーニングを説明します。自分で解決できるようになるのが1番です!
2. リンパ性によるむくみ(リンパ液の障害)
原因
- 手術後やリンパ節郭清術後のリンパ浮腫
- 慢性炎症や感染症
特徴 進行すると非圧痕性(強く押しても後が残らない)、片側性が多く、慢性的で進行性。だんだん皮膚が硬くなっていくことも特徴です。リンパシンチグラフィーやICG検査が確定診断に有効とされています。
対策
- リンパドレナージ:専門家によるリンパマッサージでリンパ流を促進
- エビデンス: マニュアルリンパドレナージはリンパ浮腫の症状を軽減するのに有効(Földi et al., 2003)。加えて着圧タイツなどの圧迫療法も有効とされています。
- 運動療法:リンパ流を促す軽い有酸素運動(ウォーキングや水中運動など)やレジスタンストレーニング
- エビデンス: 運動がリンパ液循環をサポートし、むくみを軽減する可能性があることが示されています(Yoon et al., 2016)。
- 体位管理:足を心臓より高く挙げて休む(10〜15分程度)。特にむくみがひどい場合や、座っている時間が長い人はこのような方法も有効です。
↓↓↓↓↓↓↓↓
タイチ院での対応:
リンパ節郭清術後などであれば鍼と整体で全身を整え、適切なレジスタンストレーニングによりむくみを抑えることができます。しかし、進行性のものであれば医療機関へご紹介することがございます。
3. 食事・栄養の影響によるむくみ
原因
- 塩分摂取過多による体液貯留
- 低アルブミン血症(低栄養)
対策
- 塩分制限:減塩を心がける(疾患によっては1日6g)
- エビデンス: 塩分摂取量を減らすことで体液貯留が軽減される(He et al., 2013)。
- タンパク質摂取:低アルブミン血症の場合は、魚・卵・豆類などでタンパク質を補給
- エビデンス: アルブミン値がむくみに関与していることが指摘されている(Ballmer et al., 1997)。
タイチ院での対応:残念ながら当院には食事・栄養の専門家は在籍しておりません。その場合、管理栄養士に相談できる医療機関をご紹介いたします。まずは減塩から心がけましょう!食生活がむくみに影響している方は多いです。
4. ホルモン変動によるむくみ
原因
- 妊娠、月経前症候群(PMS)、更年期などでホルモンが体液バランスに影響
- 薬剤(ピルや降圧薬など)の副作用
対策
- ホルモン調整:必要に応じて医師に相談し薬剤を調整
- 適切な水分摂取:体液バランスを保つために1.5~2L/日の水分を摂取
↓↓↓↓↓↓↓↓
タイチ院での対応:
PMSや更年期による体液バランス異常であれば、鍼灸治療が効果的です。適切なツボへのお灸と鍼の施術を行い症状の緩和を図ります。また、薬剤性による副作用のむくみであれば一度専門家のいる医療機関への受診をお勧めいたします。
5. 心臓や腎臓の機能低下によるむくみ
原因
- 心不全、腎不全による体液バランスの乱れ
対策
- 医師の診断・治療:基礎疾患を特定し、適切な治療を受ける
- 利尿薬の使用:医師の指示のもとで利尿薬を使用し、過剰な体液を排出
- エビデンス: 利尿薬は心不全や腎不全によるむくみを軽減する(Yancy et al., 2013)。
- 心臓・腎臓による機能低下によるむくみであれば医療機関での薬物療法を行いましょう。
・この場合、ドレナージや、マッサージ、下肢挙上等は、循環量を上昇させ心臓に負荷がかかるため禁忌です。
タイチ院での対応:この場合鍼灸・筋膜整体での効果は低いです。適切な医療機関への受診をお勧めいたします。
6. 肥満によるむくみ
原因
- 体重増加による下肢への圧力増大。
- 静脈還流やリンパ流の阻害。
対策
- 減量:バランスの取れた食事と運動で適正体重を維持。
- エビデンス: 減量によって下肢の浮腫軽減が確認されている研究があります(Ryan et al., 2004)。
- 筋力強化:ふくらはぎや大腿の筋肉を鍛え、循環を促進する。レジスタンストレーニングが有効
↓↓↓↓↓↓↓↓
タイチ院での対応:
まずは、代謝を向上させるため全身の可動域拡大をハリ✖️リハ(鍼と理学)にて行います。その後、整体・トレーニングを通して動ける身体づくりを行い、ご自身でもできるトレーニングを指導いたします。
7. 熱中症や高温環境によるむくみ
原因
- 高温下での血管拡張による体液の漏出。
- 発汗過剰による体内のナトリウム濃度低下(低ナトリウム血症)。
対策
- 体温調整:涼しい環境を確保し、直射日光を避ける。
- 水分補給:適度な電解質(ナトリウムやカリウム)を含む飲料を摂取。
- エビデンス: 電解質飲料がむくみの軽減に有効であると示唆されています(Sawka et al., 2007)。
- 通常のむくみとは異なり、これらの場合は適切な見極めが必要です。その他身体所見がある場合は医療機関へ受診をしましょう。
8. アルコール摂取過多によるむくみ
原因
- アルコールによる血管拡張。
- 尿量増加後の体液再吸収の乱れ。
対策
- アルコール摂取制限:週に数回の禁酒日を設定する。
- 水分補給:アルコール摂取後に適切な水分を補う。
飲んだ翌日、顔や手足がパンパンになっていることがありますよね。飲み過ぎ注意ですね!
9. 薬剤性のむくみ
原因
- 一部の薬剤(降圧薬、ステロイド、NSAIDsなど)の副作用による体液貯留。
- カルシウム拮抗薬(降圧薬):末梢血管拡張作用によりむくみが生じることがある。
- ホルモン治療薬(ピル、HRT):体液保持を引き起こす可能性。
対策
- 医師の相談:必要に応じて薬剤の種類や用量を調整。
- 体位管理:足を高くするなどで一時的な軽減を試みる。しかし、一時的な処置に過ぎないため、すぐにかかりつけ医に相談を。
・これは薬剤性のむくみだ!という判断はむくみの要因が多い場合判断できません。ただ、多くの薬を服用されている方であればその中に副作用としてむくみが出現することがございます。まずは、薬を処方された医療機関にて薬剤性のむくみが影響しているか判断してもらいましょう。
10. 座りすぎや立ちすぎによるむくみ
原因
- 長時間同じ姿勢でいることによる血液循環の停滞。
- 筋ポンプ機能が働かず、足に体液が溜まる。
対策
- ストレッチ・運動:1時間ごとに立ち上がって軽い運動を行う。
- 適切な姿勢:長時間椅子に座る場合は、足首を動かしたり、少し立つだけでも効果的です。また、フライト中のDVT(深部静脈血栓症)は有名ですよね。その場合も、足首を動かす、トイレへ行くなどすると予防に繋がります
・高齢者に圧倒的に多いですが、デスクワーカーにも多いです。隙間時間や休憩時間に軽く立ち上がるだけでも違いますよ!
↓↓↓↓↓↓↓↓
タイチ院での対応:
股関節・膝関節、特に足首の動きを大きく改善させていきます。ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)は、第二の心臓と呼ばれるほど、心臓へ血液を戻すポンプ機能があります。この筋肉がきちんと働くためには、まずは足首の可動域の確保が重要です。その後に適切な筋力トレーニングや、運動を行うことで効果が現れます。
11. 妊娠によるむくみ
原因
- 子宮の拡大による下肢静脈の圧迫。
- ホルモン変化による体液保持の増加。
対策
- 体位管理:足を高くして血流を改善。
- 着圧ソックスの使用:妊娠中の静脈還流を助ける。
- 医師への相談:むくみが異常にひどい場合は妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)の可能性を確認する。
・定期検診の際に、足のむくみがある際は都度相談してみましょう!
12. 内臓疾患(肝臓・甲状腺など)によるむくみ
原因
- 肝疾患(肝硬変など):アルブミン産生低下により血液の膠質浸透圧が低下し、むくみが生じる。
- 甲状腺機能低下症:代謝低下により組織間液が蓄積。
対策
- 早期診断・治療:専門医に相談して基礎疾患を治療。
- 食事療法:肝機能や甲状腺機能をサポートする栄養を摂取(低ナトリウム、高タンパクなど)。
・これらの場合は、適切な薬物療法に加え、食事療法も重要です。医師・薬剤師・管理栄養士にご相談ください。
13. 筋骨格系のによるむくみ(筋肉の影響)
原因
- 捻挫や打撲などの外傷に伴う炎症性浮腫。
- 長期間の筋肉の不活動による筋ポンプ機能低下。
対策
- RICE処置:Rest(休息)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)。外傷直後の対応です。
- 適度な運動:筋肉を徐々に動かし、血液・リンパ流を回復。
↓↓↓↓↓↓↓↓
タイチ院での対応:
捻挫や打撲などの外傷性によるむくみの場合、鍼治療が有効です。直接的に鍼で刺激をいれ、炎症している組織の修復力を高めることができます。また、廃用性(長期間動かなかったことのよる)であれば、まずは全身的な動きの再獲得から図ります。そこが確保できたら局所への適切なトレーニングを行い、自身でできる日々の運動まで細かく指導させていただきます。
14. ストレスや生活習慣の乱れによるむくみ
原因
-
自律神経の乱れ
- ストレスや不安によって交感神経が過剰に働き、血管が収縮したり、体液バランスが崩れる。
- 副交感神経が十分に機能しないことで、血液やリンパの循環が滞る。
-
過呼吸や過換気症候群
- ストレスや不安により過呼吸が起こると、血液中の二酸化炭素濃度が低下し、血液のpHが変化。これが体液のバランスに影響を及ぼす。
-
ホルモンバランスの変化
- 心因性ストレスが慢性的に続くと、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が増加し、ナトリウムや水分が体内に保持されやすくなる。
-
精神的負担による行動パターン
- ストレス下での水分摂取過多や塩分の摂取増加。
- 運動不足や不規則な生活習慣による血流停滞。
症状の特徴
- 朝よりも夕方や夜にかけてむくみが強くなることが多い。
- 身体の他の部位に異常がなく、血液検査や尿検査でも異常が見られない。
- 精神的な負担が高まるとむくみが悪化し、ストレスが緩和されると軽減する傾向がある。
・ストレスによって、むくむというより、ストレスによる暴飲暴食、睡眠不足、ホルモンバランスの変化による影響が大きいです。1〜8で説明したような状態のむくみにならないよう、ストレスコントロールも重要ということですね!
↓↓↓↓↓↓↓↓
タイチ院での対応:
”温活”お灸コースをオススメします。体質に合わせた身体のツボを確認し、お灸と呼吸法、整体などを用いて、強制的に副交感神経を引き上げリラックス状態に誘います。交感神経が優位とした状態は、仕事などの集中する際や、スポーツをする際必須です。しかし、その状態が1日中続くのが問題なんです。心身状態がしっかりon/offができるよう様々な技術を駆使してサポートいたします。
まとめ
足のむくみに悩む人は多いですが、その原因はさまざまです。ただの水分摂りすぎや運動不足だけではなく、静脈還流の低下やリンパ液の障害、ホルモン変動、内臓疾患などが原因になることもあります。
タイチ鍼灸接骨院では、むくみの原因を丁寧に分析し、症状に合わせたアプローチを行っています。例えば、筋肉や関節の動きを改善し、血流やリンパの流れを促進する「鍼✖️リハ(鍼と理学療法)」を用いた施術や、日常で取り組めるセルフトレーニングをお伝えしています。
むくみの種類によっては、医療機関での診断や専門的な治療が必要な場合もあるため、適切な判断とケアが重要です。
熊本市北区にありますタイチ鍼灸接骨院は、むくみ改善のお手伝いを通して、皆様の健康と快適な生活をサポートします。お気軽にご相談ください!
当記事は、健康に関する理解・知識を深めるためのものであり、特定の医学的見解・治療法を支持・推奨するものではございませんので、ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
タイチ鍼灸接骨院
861‐8081
熊本県熊本市北区麻生田2‐3‐7
電話番号 : 096‐339-5477
----------------------------------------------------------------------